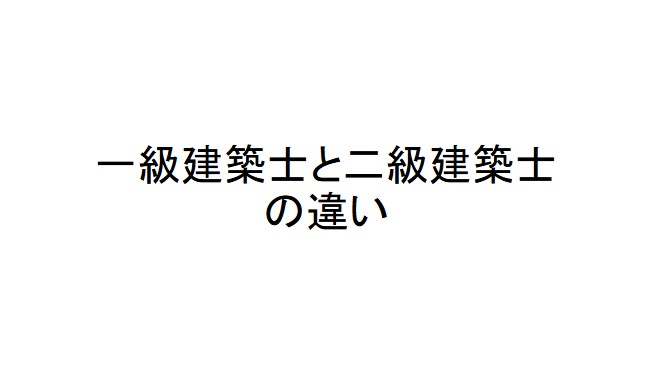試験の違い
実務経験
二級建築士は、「大学、短期大学、高等専門学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校において、指定科目を40単位以上履修して卒業した者」
であれば、合格後、実務経験なしで免許登録ができます。
一級建築士は、「大学、高等専門学校(「本科+専攻科」の卒業者に限る。)、職業能力開発総合大学校(長期課程又は応用課程の卒業者に限る。)、職業能力開発大学校(応用課程の卒業者に限る。)、専修学校(専門課程で修業年限が4年以上のもの)において、指定科目を60単位以上履修して卒業した者」
であれば、合格後、実務経験を2年積むと免許登録ができます。
※どちらも学校種別・単位数により条件が異なりますので、詳細は下記を確認してください。
↓建築技術教育普及センターのページです↓
二級建築士・木造建築士の受験・免許登録時の必要単位数(学校種類別)
令和2年の建築士法改正により、実務経験が試験前ではなく免許登録前に求められるようになり、
より若い年齢でも試験を受けられるようになりました。
学科試験科目
二級建築士の学科試験は、
「建築計画」「建築法規」「建築構造」「建築施工」の4科目。
出題数は合計100問各科目25点満点、4科目合計100点満点の試験で、
出題形式は5肢択一のマークシート方式です。
一級建築士の学科試験は、
「計画」、「環境・設備」、「法規」、「構造」、「施工」の5科目。
出題数は合計125問で総得点が125点満点の試験です。
出題形式は4肢択一のマークシート方式です。
製図
二級建築士の製図試験は、設計課題の構造種別は「木造」または「RC造」で
これまでの傾向では3年に1度RC造の年があります。試験時間は5時間です。
一級建築士の製図試験は、設計課題の構造種別は「RC造」のみです。
試験時間は6時間30分です。
製図試験は、学生の頃に経験する通常の試験勉強とは異なるため、
合格するための勉強方法の再現性が難しく、難易度が高いとされています。
業務での違い
業務範囲
二級建築士は、比較的小規模な建築物についてのみ設計・工事監理を行うことができます。
例えばRC造3階建てなら延床面積300㎡以下までといった制限があります。
一級建築士はそのような制限なく、全ての建築物について設計・工事監理を行うことができます。
業務範囲の詳細は下記の建築技術教育普及センターのページを参考にしてください。
資格手当
いくつかの企業の資格手当を調べてみたところ、
二級建築士は、月5,000~8,000円
一級建築士は、月10,000~30,000円が多いようです。
有資格者を急募している企業では更に手厚い手当も見かけました。
実務で嬉しいことがある
一級建築士を持っていて名刺に資格を書いていると
名刺交換の際に十数回に一回は「おお!一級建築士さんですか!」だったり
「一級建築士持ってるなんて凄いですね〜」なんて反応をいただけたりします。
個人的には、この瞬間が1番「資格を取って良かったな~」と実感する場面です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらのブログでは、一級建築士、F1、車、旅行に関することを中心に
役立つ情報をまとめていきます。今後ともよろしくお願いいたします。