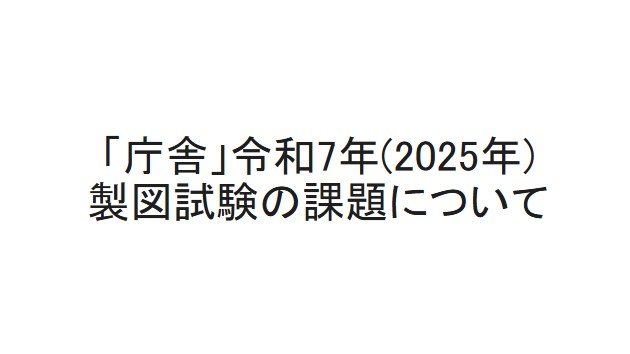令和7年(2025年)の一級建築士製図試験の課題が発表されました。
課題:庁舎
令和7年の一級建築士製図試験の課題は「庁舎」です。
“令和7年一級建築士試験「設計製図の試験」の課題を公表しました”(公益財団法人建築技術教育普及センター)https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-seizu.html
庁舎の役割
庁舎について調べてみると、下記のような役割が求められるようです。
庁舎は、市民が来庁して様々な行政サービスを受ける場であるとともに、市民生活を支える活動が行われる場であり、全ての市民にとってのよりどころとなります。 また、災害などに対する危機管理センターとなることが庁舎の最も重要な役割と考えられることから、市民が安心して日常を送るよりどころとなります。市民力と地域力を基礎に置いて、市民や地域、企業、団体などが行政とも連携、協働してまちづくりを進めていく拠点となります。
引用:1 新庁舎の⽬指すべき姿
平時は市民が行政サービスを受ける場、行政と市民・企業の交流の場、
災害時には市民を守るための拠点となる施設となります。
庁舎の要求事項
行政サービスとして、市民課、福祉課など市民が訪れる窓口と執務スペース
交流スペースとして、カフェやラウンジ
議会機能として、議員控室や議場が求められると思います。
他にも災害対策として、非常用電源設備などの要求もありそうです。
市民が訪れる窓口に隣接する執務スペースとのセキュリティ対策も重要な観点となりそうです。
出題されそうな内容
建物の規模感として、大きな市町村の役所としての機能を求められる建物の場合、
1棟の建物で全ての機能を満たすという条件だと
過去の一級建築士製図試験の建物規模を大きく上回りそうです。
(各年度の標準回答例①の延床面積:令和6年5,038㎡、令和5年3,039㎡、令和4年5,941㎡)
(参考例:水戸市役所40,942㎡、浦安市役所25,680㎡)
そのため、そのような場合は「分庁舎」として部分的な機能を持った建物になりそうです。
人口の多くない市町村の役所となると規模が小さくなるため、
1棟でも機能を満たすことはできそうです。
(参考例:裾野市役所6,436㎡(人口約4.8万人)、備前市役所6,658㎡(人口3.8万人))
職員数が何名、1日の来庁者が何名といった人数から
必要面積を算出する等の知識も求められるかもしれません。
また、試験元の発表している留意事項にも
「大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画」と記載されており、
耐震性の確保なども焦点となりそうです。
求められる役割によって課題の自由度が変化するのではないかと予想します。
自由度の高い課題の場合は、市民のためのスペース重視の分庁舎となるのではないかと思います。
例えば、本庁舎と隣接し、行政サービスの他、カフェスペースやワークショップスペースなどを
備えているようなイメージです。
一方で、1棟で全ての機能を満たすとなると行政サービス・執務スペース・議場など複数の役割が
混在するため、ゾーニングの難易度が高いものの自由度は低くなるのではないでしょうか。
参考資料
いろいろ調べていたところ興味深い資料を見つけました。
やはり人口10万人以上の市となると庁舎の規模も大きくなるようです。
※一部建て替えの面積のみの場合もあるので、参考程度としてください。
”人口10万人以上の市の本庁舎建替えの状況 【R2.1各自治体HP調べ】”(さいたま市)https://www.city.saitama.lg.jp/006/007/002/022/004/p090277_d/fil/R2_2.pdf
最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらのブログでは、一級建築士、F1、車、旅行に関することを中心に
役立つ情報をまとめていきます。今後ともよろしくお願いいたします。